- CoDMON(コドモン)
- コラム
- コドモンの取り組み
- 先生たちの写真業務の負担をゼロに メモリー事業部が切り開く「写真」の新たな価値と未来

先生たちの写真業務の負担をゼロに メモリー事業部が切り開く「写真」の新たな価値と未来
コドモンのメモリー事業部は、これまで保育者が担っていた写真や連絡帳製本の共有や販売など、こども施設での子どもの姿や思い出をより多くの保護者に届けること、そのための先生たちの作業負担をICTで省力化するために立ち上げられた部署です。
業務省力化はもちろん、写真や連絡帳を施設、保護者、子どもの三者間での豊かなコミュニケーションのきっかけに変えていくためにできることとは? を常に問い続けています。今回は入社以来ずっとメモリー事業部に籍を置く山下(写真左)と、プロダクトマネージャーとして開発に関わる木村(写真右)に話を聞きました。
山下実樹
メモリー事業部所属。大学在学中からコドモンのインターンとして保育施設で撮影された写真や動画を保護者に共有・販売するメモリー事業部の前身となるチームに携わる。2022年、コドモンに入社。同時期に始動したメモリー事業部に配属される。
木村友哉
プロダクト開発部 プロダクトマネジメントグループ所属。プロダクトマネージャーとしてメモリー事業に携わる。教育業界、起業などの経験を経て、2022年、コドモンに入社。
写真管理はそもそも保育者の仕事ではない
メモリー事業部は何をしている部署か教えてください。
山下:メモリー事業部は、保育施設でそれまでは保育者の方々が担っていた写真共有・販売にまつわる一連の作業負担をICTで解決しようとの思いから生まれた部署です。具体的には、保育施設で保育者やカメラマンが撮影した写真を、アプリ経由で簡単に保護者と共有・販売できるサービスです。
木村:僕も立ち上げメンバーではないのですが、保育施設における写真の管理が大変なことはそれ以前からよく耳にしていました。写真の掲示や管理、集計、発注、現金回収という一連の作業は時間も手間もかかりますし、何度も確認作業が発生します。
でも、そもそも写真管理は保育者の方々の本来の業務ではないはずです。それならば現場の負担軽減を目指し、かつ売上収益の一部を施設に還元することで施設の運営支援にも貢献できるサービスができないか、との思いから始まりました。
サービスを導入した保育施設からはどのような反応がありましたか。
山下:「業務の負荷が大きく減った」という反応が多かったのは、やはり嬉しかったですね。「写真の張り出し・注文管理・発注などの業務にとても時間がかかって大変だ」との声を保育者の方たちから聞いていましたから、そこに貢献できたことに手応えを感じました。
一方で、新たに気付いたこともあります。ある先生が「普段の子どもたちの表情や頑張りを写真で共有することで、園と保護者でその子にとって何が一番よい保育かを一緒に考えられるようになりたい」と語ってくれたんです。つまり、写真共有にはコミュニケーションツールとしての価値がある。
当初は現場の負担削減ばかりに注力していましたが、メモリー事業部が担うべき主な役割は保育におけるコミュニケーションツールの提供にあるのではないかと考えるようになりました。
木村:0歳から2歳くらいの子どもは、言葉でその日の出来事をまだうまく話せませんよね。でもその日の写真をきっかけに親が「こんなことがあったの?」「○○ちゃんと仲良しなんだね」と問いかけると、そこから会話が生まれやすくなる。親と子、親と保育施設、親同士の関係性や遠方に住む家族とのコミュニケーションを深めるきっかけのツールにもなっていることが、保護者へのヒアリングからわかってきました。

山下:それまでは「今日どんなことあった?」と聞いても「忘れた~」で終わっていた子どもが、写真を見せると「これ、〇〇ちゃんとね……」と具体的に話し始めるというエピソードはよく聞きますよね。写真が親子の会話を促し、子どもの記憶を引き出す役割を担っていることは、私たちにとっても発見でした。
他に印象的な出来事はありますか?
山下:写真販売を始めたばかりの施設からは、よく「難しそうで、自分たちにできるか不安」「どうやって使えばいいかわからない」といった声を聞きます。その不安に対するリアルな答えを持っているのは、実は私たちではなく、すでに利用されている施設だと思うんです。
そこで、すでに写真販売を利用している施設のみなさんにご協力いただき、各園での使い方をまとめた記事や動画をつくりました。まだ写真販売を使っていない施設の方向けのセミナーでもご紹介したところ、「不安だったけれど大丈夫そう、できるなと思った」など、前向きなお言葉をたくさんいただきました。利用施設のみなさんと一緒につくったものが、他の施設の方に役立っているということが何より嬉しかったです。
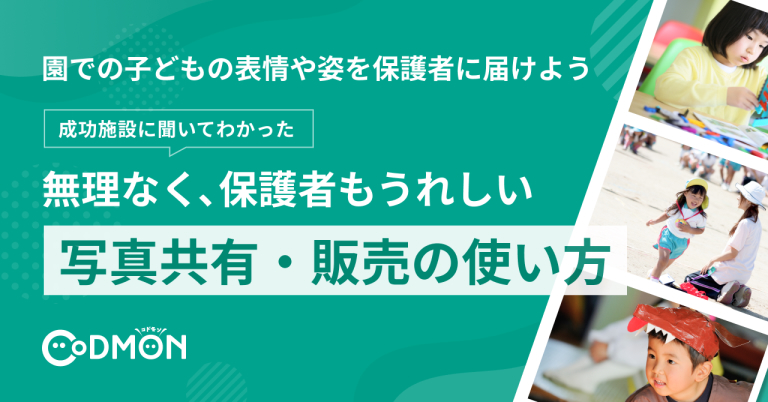
(以前行ったICTコドモン利用施設向けのセミナー)
木村:僕たちは保護者の方々へのヒアリングも積極的に行って、保護者の方にも気持ちよく使っていただけるサービスを目指しています。保育者のみなさんが、保護者に子どもたちの様子を共有しようと毎日頑張ってくださっていることやそうした温かい想いが保護者に届き、よい循環が生まれたら嬉しいなと思っています。
成長する子どもの顔の変化もAIが自動識別
新たに先生たちが使えるようになった写真お助けAI「せんせいフォト」についても教えてください。
山下:これまで保育施設における写真の仕分けや枚数調整は手作業と目視によって保育者が行うもので、かなりの時間を要する作業でした。「せんせいフォト」はその現状を解決するために独自開発されたAIを組み込み生まれた新サービスで、2025年5月から提供を開始しました。
木村:「せんせいフォト」がリリースされた背景には、AI活用によって子ども写真解析技術を開発・提供する株式会社とりんくが2024年12月にコドモンのグループに加わったことが大きく関係しています。
写真選別の負荷の高さは以前から解決したい課題としてありましたが、自社でAI顔認識機能を加えるとなると、おそらく1年以上先になっていたでしょう。その計画がとりんくとの連携によって、タイムマシンに乗ったくらいに大幅に短縮されました。

(「せんせいフォト」の利用イメージ)
山下:「写真選別が大変で、どうにか負担を減らす方法はないか」というご相談は、施設ヒアリングで以前から多く寄せられており、何とか対応せねば、という思いがずっとあったので、やっと形にできてよかったです。
木村:保育者の選別作業の負荷軽減だけでなく、保護者の利便性の向上にも大きく貢献できると期待しています。ある保育施設から「これは革命ですね!」と大変喜んでいただいたことが印象に残っています。
山下:それまでは写真選別の負荷に対して、私たちは運用でどうにかするという方法しか提案できませんでしたが、とりんくのAI技術によってその負荷を大幅に削減することが可能になりました。これまでは、アイデアはあるものの具体化が見えなかった機能開発もAI活用によって一気に加速しています。

今は種まきの時期、ここから可能性が広がる
最後に、今後実現したいことについて教えてください。
山下:保育施設を始めとした「こども施設における写真共有・販売の業務負荷」を限りなくゼロに近づけること。これはもう絶対にやりきりたいと思っている目標です。その上で、「思い出の残し方」は写真だけではない、写真以外の価値を届けるという視点も個人的に常に心に留めています。
たとえば、動画の配信や制作物の共有、連絡帳のよりよい形での提供など、写真以外の思い出も保護者にとって嬉しい形でまるごと残せるようにしていけたら。さらに、子どもたちが思い出を軸に保護者との会話を楽しんだり、先生と保護者のコミュニケーションが活発になったりするような世界を実現したいと考えています。
木村:「写真以外」の思い出にも焦点を当てていく、という意味では僕も同感です。子どものその日の様子をただ伝えるだけでなく、例えば時系列に沿ったストーリーに仕立て上げてその子の成長の「物語」として受け取れる。そんな形が実現できないかなと考えています。
他にも、一度購入した写真や見た動画を日常の中で思い出しやすくするような仕組みや、配信元がそれぞれ違う写真を一元的に管理して手元に残せる機能も検討中です。
業務負担の削減のような目先のことだけでなく、「5年後の未来」のように抽象度の高いテーマについても話し合い、よりよいサービスにしていけたらと思っています。
山下:私たちが目指すのは、日々の保育現場の「困りごと」の解決です。施設のみなさまからの要望や率直なご意見を一つひとつを真摯に受け止め、改善に向けて今後も努力を続けていくつもりです。
木村:コドモンの写真販売は、保護者の方々に写真をご購入いただいた金額の一部が、保育施設に還元される仕組みになっています。先生方が頑張って撮影し、届けてくださった子どもたちの様子が、家庭にとっての価値となり、そこから生まれたお金が保育業界に循環する。
この循環をさらに大きくし、社会と保育の価値が共に高まる世界をつくっていきたいと強く思っています。

関連ページ
・コドモンの写真共有・販売について
・「せんせいフォト」プレスリリース
NEW
新着記事
- CoDMON(コドモン)
- コラム
- コドモンの取り組み
- 先生たちの写真業務の負担をゼロに メモリー事業部が切り開く「写真」の新たな価値と未来





